おはようございます。
運動競技大会では、クラスで301回の記録を出すことができました。
これは見る人から見ると平凡な記録かもしれません。でもボクらのクラスにとっては、サイコーの記録だったんです。
学校によっては全校で取り組む3分間の長縄8の字跳び。この指導に悩む人も多いのではないでしょうか。
- 長縄をクラスでどう指導すればいいのかわからない先生
- 自主性に任せる?担任が教える?そのバランスに悩む先生
- 子どもたちが心から喜ぶ顔が見たい先生

あお
こんな先生たちに、子どもたちと一緒に新記録に挑んでもらえたら幸いです!
「最高記録を生み出すまでのプロセス」について、記録の意味も込めて書いていきたいと思います。
長縄の競技性から考える学級経営
目次
関係性の充実が生み出す、長縄への気持ち

この時は6年生担任。10月の大会でした。
クラスとして、関係性が充実してきているのは感じていました。
全体の一体感というよりは、個々のつながりあって、いい雰囲気を生み出している感じ。普段はバラバラしているけど、こういう何かの目的がある時には、ぎゅっと固まる感じ。今の状態がボクは理想だと持っています。
長縄やろー!!

子どもたち
っていう雰囲気が自然に流れていました。「やりたくないなぁ」が見え隠れすることが少なかったのです。
根底には、今まで積み上げてきたものが間違いなくあるはず。
途中、順番が遠いペアと見合うことになった時も、誰しもがお互いの良さをフィードバックし、アドバイスをすることができていました。
長縄の技能だけを追究しても、意味がないんだよね。

まーくん

あお
長縄を通して、何を達成したいのかが大事じゃないのかな。大人になって長縄の技能は必要ないからね。
誰とペアでもコミュニケーションの一定の水準を保てることは、ペアづくりの積み重ねが生んでいるのです。
ペアでの信頼感・安全性が根っこにあるから、記録自体も伸びていくこと、まず第一にそれを知ってほしいです。
この他のクラスのベースを作った実践を載せています!
価値のある振り返りが、長縄への意欲を高める

練習期間を通しての、長縄を行なった後の振り返りが充実していました。
個別にジャーナルで振り返りを行なっていても、一人で2ページ、3ページなんて書く子が増えてきました。ものの5分そこらで、みんながぎっしり。こっちが驚かされます。
体験が大きければ、振り返りも充実する。それはわかっていたけれど、ここまで書くとは…
サークルになっての全体の振り返りでもいい雰囲気で、次への一歩がたくさん出てくる。
それを長縄プロジェクトの面々が上手く活かしながら、練習を進めていました。
時にはこんなこともあったけれど、それすらも、さらっと乗り越えていった子どもたち。
こうやって振り返りによって、次へのステップが決定されていく。先生も振り返りのアイディアを出す一員です。
また、実行委員が回数の記録と、コツと、目標をまとめたものを、作ってくれました。コツは技術的なことと、心構えを書きながら、ここにためていく感じです。

ここで出てきた心構えは日常のビーイングとつながっています。また終了後にビーイングに入れるものとして、残しておきたいものを選択します。

今回は、終了後にたくさんのビーイング候補が出てきました。それだけ大きな体験だったということです。
ビーイングについてはこちら!

あお
コツを先に載せなかったのは、長縄で必要なのは、技術だけじゃないからです。回数が上がったとしても子どもの気持ちがそこにないと、なんら意味はありません。
長縄八の字跳びのコツや練習方法


あお
長縄って自分だけが跳べてもダメ。自分の後ろ3人がスムーズに連続跳びができていればOK!
最初のうち、口すっぱくして言っていた言葉です。長縄ってそう言う競技だと思っています。
個人競技ではなく、他の人にほんの少し気遣いや協力できるかどうかにかかっている…
クラスづくり、そのものなんです。
個人の目標、幸せのために生きていくのが自然な姿、学級のためじゃない。
でも、お互いの幸せのためにできることはあるし、相手の幸せを願っていると自分も巡り巡って幸せになる。自分の幸せを最大化させるためには、他者の幸せにも心を置かないといけない…
だから、クラスでいることの価値が大きいんだよ、といつも話しています。
技術的に確認したこともあります。
今回は「iPadのスロー映像」で自分たちの動きを撮影しながら、振り返りの際に見るようにしました。
また良いイメージを見せるために、youtubeから動画を引っ張ってきて、見せました。
この動画はよく見せて参考にしたなぁ。とっても上手でいくつか子どもたちがコツを見つけることができました。
子どもたちが見つけたコツに加えて、指導することは次のことです。
- 縄の真ん中で跳ぶ
- 回し手(ターナー)のすぐ横から入って、すぐ横を抜けていく
- 跳んでいるときになるべく縄に当たらないように、90度体を回転させる
- 1周りしたら反対側から跳ぶため、ターナーが少し移動して、跳ぶ人の入射角を大きくする
- 跳ぶ時はなるべく片足跳びで、着地の後すぐに抜けるようにする
これらのことは、youtubeの動画を見るとよくわかるかと思います。
先生が教え込むことではないんだよね。子どもに気付いてもらいたいこと。

まーくん
また練習も3分間を毎回測るのではなく色々なバリエーションで行なっていました。
- 1分間で100回を目指す
- 連続跳びが3回途切れるまでの回数をあげる
- 連続跳びの最高記録を目指す
- ノーミスで1周(35人)が跳ぶのが、3回できるまでのタイムを縮める
様々な練習方法があります。子どもたちのアイディアをもらいながら、練習の練習にならないように工夫していくことが大事です。
練習の種類が豊富ということは、子どもたちにとってもいいことですよね。この練習とそれがなぜ行われているのかを共有していくことが大事かなと思いました。
低学年の場合も考え、長縄への指導はこちらにまとめました!
長縄跳び、本番までのモチベーションの保ち方

子どもたちの感情面も非常に大切になってきます。
学習や競技において、「感情」によって大きく左右されること、最近は強く実感しているんです。
長縄におけるモチベーションをどう保つかは今回、たくさん考えました。
最初は、高学年なので、誰かのモチベーションが下がるかと思ったのです。
でも、連続跳びができない子に声をかける子が多くて…技術的なことや振り返りを紹介するうちに、誰もが長縄に前向きに取り組んでいたのには驚かされました。

あお
こんな方法もあるんだと最初に6年生を担任した時の自分に教えてやりたい!
速いスピードに慣れるまでの時間は長かったけど、慣れたら一気にモチベーションが高まりました。記録が上がることは、当然ながらモチベーションアップにつながっていきます。
今までで初めて、ご褒美をあげたいなぁと思ったのです。「もので釣る」ことは徹底的に避けていたボク。
今回、そう思ったのは、この子たちの長縄に対する気持ちがまっすぐで、やる気に満ち溢れていたからです。
達成できたらそれ相当なものがあってもいいんじゃないかとってこと?

まーくん

あお
モチベーションがすり替わることはないと思ったんだよね。
子どもたちと相談して、第一目標の250回達成で「宿題なし1日間+PA1時間」。第二目標の300回達成で、「宿題なし3日間」。
宿題いいから、先生の家にみんなで行く!!

子どもたち

あお
それ、却下!
笑い合いながら、またモチベーションが高まっていきました。
あとは、ペアクラスである1年生の応援かなぁ。
大会前日、1年生の前で披露したら、最高記録の273回が出ました。「いいところ見せる」ことは、大きなモチベーションになるっていうことが、子どもたちの凄さです。
いざ長縄本番!当日の最高記録は??

ボクが嬉しかったのは、ずっと練習には入れなかった交流級の児童と共に、ベストの記録(301回)が出たこと。 その子にとって大きな自信になったし、クラスにとっても大きかった。
終了後、ビーイングに入れたい言葉には、本当にたくさん出てきました。それぐらい子どもたちにとっては大きな体験だったのです。
まとめ 夢のようなサクセスストーリー

子どものジャーナルに書いてあった言葉より。
なんか、このままドラマになりそうなくらい、長い長い「ロングサクセスストーリー」がありました。ケンカしたり、協力したり、努力したり、時にはきつくなったりしたけど、301回いったときは、言葉にできないくらい嬉しくてたまりませんでした!
児童の振り返りジャーナルより
ボクも本当に同じ気持ち!これはドラマになる!
この振り返りを書いた子は、大好きな漫画に長縄物語としてまとめて、学級通信に連載をしたのでした。卒業前に書ききった漫画は本当に素晴らしく、今でもこのクラスの宝物です。

あお
いかがだったでしょうか?
この年の1年間でも、長縄がターニングポイントだったと思います。この一体感、成功体験があったからこそ、卒業式までみんなで進んでいけたのだと、ボクは思うんです。
1つの行事にすぎないのですが、そこにどう力を入れ、子どもの力を信じ取り組んでいけるか…
この仕事の醍醐味の1つではないでしょうか。
記録だけじゃない、クラスの気持ちの団結だけじゃない、その両方が生まれた時にすごく喜びに変わるんだなぁと思いました。
正直どちらかなら簡単です。
記録だけ出てクラスがバラバラ、気持ちが一致してるけど記録は出ない…でもそこを超えていくことにこそ価値があるんだなぁと思っています。

あお
ぜひ、挑戦してみてください!
この年の6年生のクラスでやっていたことを元に、経験談から「学級をデザインすること」の重要性を書いてみました。
長縄の競技性から考える学級経営

あお
それでは今日も良い一日を!
ビーイングについても詳しく!学級経営のことを学ぶ10冊!
長縄の指導について、低学年での記録達成も含めてまとめました!




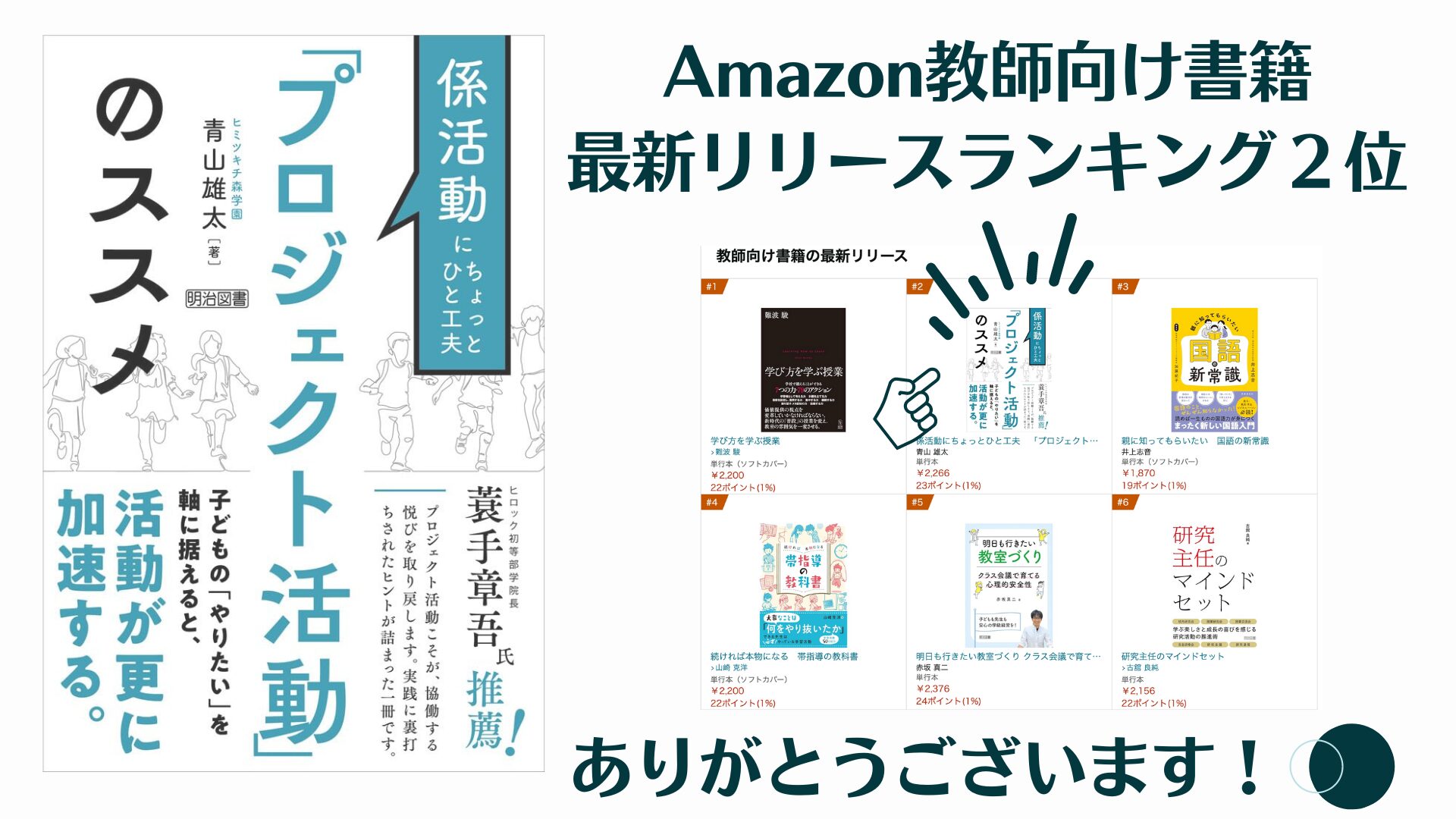




2 件のコメント
すごい!まだ300回行ったことがないな〜。
参考にさせてもらいます!!
ありがとー!泣いている子も多かった。6年生やるときはぜひ!