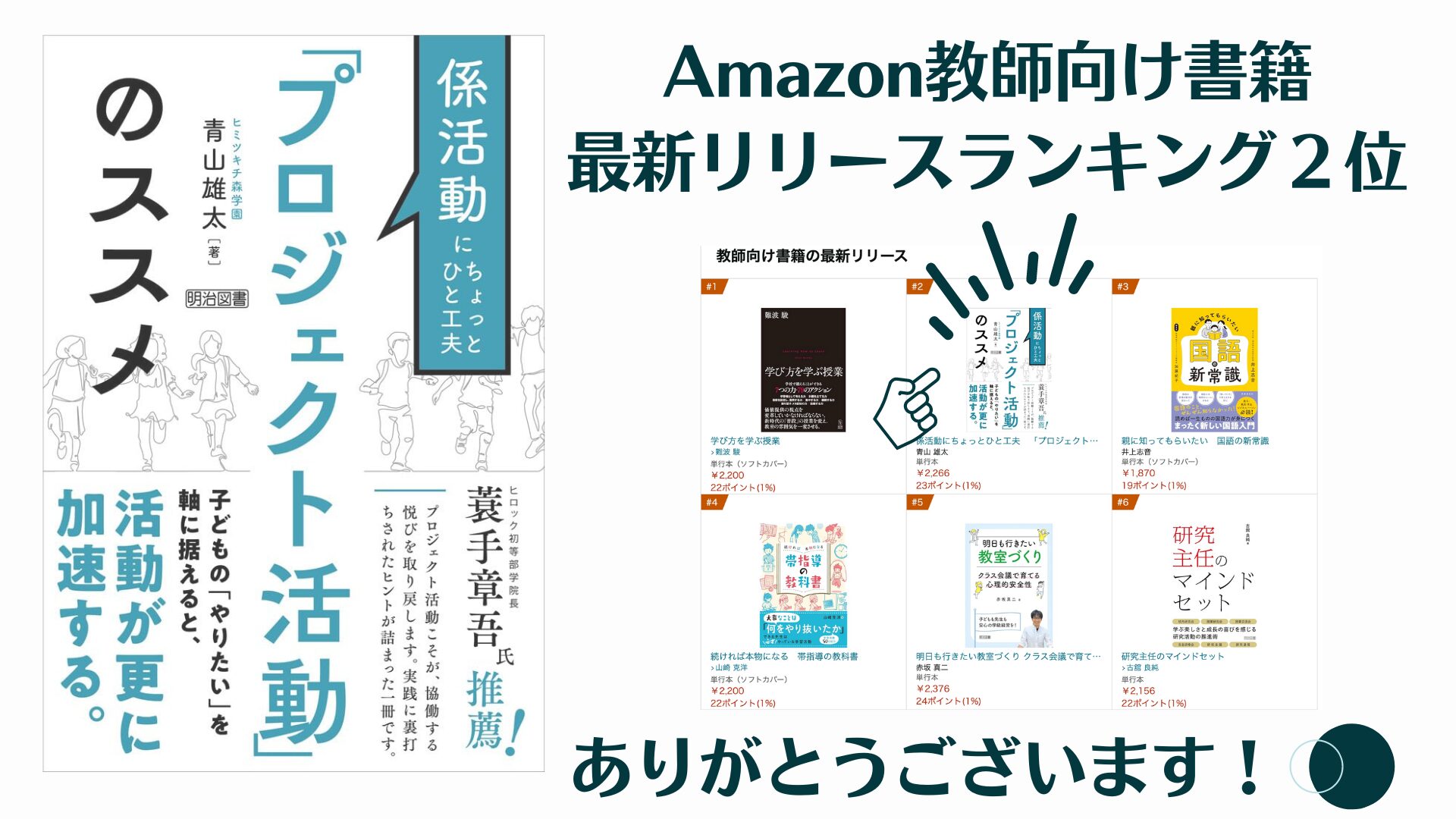おはようございます。
春の海に4人も飛び込むヒミツキチ森学園のグループリーダーあおです。釣りをしている方がびっくりしていました(笑)
さて、今日は低学年の教室についてです。
2年前に、久しぶりの低学年の担任をやっていました。そこで久々に感じたこと、初めての2年生担任として、気をつけなくてはいけないことを書きました。
中学年や、高学年をしていると、忘れてしまう感覚があるんだね。

まーくん

あお
そうなんだよ、特に初めての1年生と違う部分もあるから、気をつけなくちゃいけないんだ。
書き残しておこうと思います。低学年が多い先生には当たり前のことかもしれません。初めて低学年という方を想定して書いておりますので、お願いいたします。

あお
それでは早速見ていきましょう!
目次
低学年ははみ出すことを面白がろう!

低学年は失敗する生き物です。
そういう失敗を面白がれる人でありたいと思うんです。
ある子が給食の配膳後にバケツの水をこぼしてしまいました。教室中が水浸しに。。。
低学年の子は喜んで力を貸してくれます。こぼしちゃった子も涙ぐんでましたが、一生懸命友達と水を拭いているうちにニコニコ顔が戻ってきました。
おかげで、ぞうきんがピカピカだよ!

子どもたち
そういうおおらかさを低学年の子は持っています。
一緒に面白がればいいんですよね。
体育の世界では、「低学年は場で追い込む」って言います。言葉や状況で難しいものを作るんじゃなくて、楽しい中で自然と難しい技にも挑戦できるように、場の工夫をするということです。
これは体育に限らず、他の学習にも言えること。
他の学年よりミニテストを多くしたり、○級シールなどで挑戦する場を作ったり、自然と環境を作ることによって、難しいことに挑戦しているっていう感覚を大事にしたいと思っています。
「気づいたら難しいのができていた!」ぐらいがちょうどいいのかもしれませんね。
多少いびつでも成功体験を積み重ねる

低学年は多少の不恰好さがありつつも、成功体験を積み重ねることに重きを置きましょう。
完璧じゃなくてもいい、多少失敗していてもいい、それでも「できた!」って感覚を積み重ねていくことが大切です。
そこには先生のスルーする力も大事になってきています。完璧にきちっとである必要はありません。小さな行動を見つけることも大事ですが、それを流すこともおんなじぐらい大切です。
「なんだかんだでうまくいってるよね!自分」って感覚で進んでいくのが大事になります。
結構、ここで追い込んじゃったり、逆に自分(先生)が悩んじゃったりする人が多い気がする。。。

まーくん
そして、うまくなること、できるようになることが大好きな子どもたち。
何度も繰り返し、繰り返し、できることを味わうのも、低学年は嬉しいんですよね。
同じことでも繰り返しちゃう、きっと読み聞かせを何度もせがむように。
楽しいこと、嬉しいことは繰り返したくなっちゃうんです!

あお
ここ、忘れたくないポイントですよね。
大人は一回できたらOKなんですが、子どもは何度もしたくなっちゃう。それって大事な感覚です。
自分が良くなることの積み重ねでクラスが良くなる

そしてクラスがよくなることよりも、まずは自分がよくなることを第一に積み重ねていきましょう。
○級のシールについては、おにぎりママさんのショップで購入することもできます。これは本当にオススメです!
ボクも算数「長さをはかろう」の単元で、早速昇級シールを使わせてもらいました。
夏以降ある「九九」でも使い倒しました!

あお
ママさんの商品は一筆箋をはじめ、本当におすすめ。
個人がよくなることに、ゆるやかにつながっているみんなで取り組むこと。ここは、どの学年に限らず大事にしていきたいことですよね。
「個人がよくなる」を積み重ねる中で、クラスがよくなることにつなげていきたいです。
生理現象は仕方ない!

「先生、おしっこ!」
まぁ、これは仕方ないですよね。
おしっこや給食については、一応声をかけますが、無理はさせず、いずれできるようになるのを気長に待つスタイルですね。
ここに目くじらを立ててもしょうがないところです。
生理現象はしょうがない。声かけの繰り返しでちょっとずつ、成長すればいいんです。

あお
できた時に、みんなで祝いましょー!あ、給食の方ですよ(笑)
まとめ 低学年は無理せず戦略的に

低学年は無理をせずに、その場で動かしたくなる気持ちをグッと抑えて、次の戦略を練っていくことが大事です。
「いや、でもそれって無理だよなぁ」があったら、その場でなんとかしようとするのではなく、一旦置いて次の手を打ってみましょう。
この手を打ち続ける根気良さみたいなもんが、低学年の先生には必要なんですよね。
決して楽じゃないんだね、低学年も。

まーくん

あお
はい、全く。低学年には低学年の難しさがあります。楽しさも同様ですね。
そこもひっくるめて面白がれるかどうかですよね。
それが魅力でもあります。
楽しんで前を向いていきましょー!

あお
それでは今日も良い一日を!