おはようございます。
横浜をつなげる30人に当選したヒミツキチ森学園のあおです。葉山だけじゃなく地元横浜にも貢献します。
今日はPAについてです。
ん、PA?パーキングエリアのこと??

まーくん

あお
子どもと同じこと、言わない!PAは「プロジェクトアドベンチャー」のことなんだよ。
PAとはプロジェクトアドベンチャーのこと。
今日はプロジェクトアドベンチャーとは何か、その効果はどのようなものか、実践はどのように行なっているのかを見ていきましょう。
早速、どうぞー!

まーくん
目次
プロジェクトアドベンチャーって何?

PAについてどれだけ皆さんは知っていますか?アンケートを取ってみました。
やってる先生が3割、やっていない先生が7割ですよね。知らない先生も多いってことがわかりました。

あお
アンケート、本当にありがとうございました。
ボクにとってはPAを知れば、先生をやる楽しさが倍増する!ぐらいに思っているものです。しかも、楽しさだけじゃなくて、子どもの持つ可能性が広がっていきます。
そ、そんなに!?

まーくん
PAについては、PAJ(プロジェクトアドベンチャージャパン)という素晴らしい組織が日本にはあるので、そちらに説明を委ねたいと思います。
HPによるPAの説明
人の器を大きくすることを目指し人の成長を目指すプログラムです。人は様々な「気づき」を経て成長していきます。人が成長するためには「信頼関係」がなにより大切で、信頼関係づくりはチームビルディングでもあります。信頼関係は学習の環境としても最も大切なもので、気持ちが閉じられたままでは、成長のための「気づき」はうまれません。時には、自分の限界を超える挑戦をすることも成長のためには必要です。そのような挑戦をささえてくれる仲間の存在であり、「気づき」を成長に導くのがPAプログラムです。
PAJのHPより
気づきを成長に導くためのプログラムのことなんですね。これは元々の野外の活動でもそうですし、教室の中でできるサイズに縮小したものもあります。
ボクはPAを行う際は2冊の本を参考にしています。
これらの本は、ipadの中にも入っていますし、教室と家に1冊ずつ置いてもいます。それぐらい価値のある2冊です。
プロジェクトアドベンチャーを知ったきっかけ
ここに載っている、岩瀬直樹先生(ゴリさん)、甲斐先博史先生(KAIさん)、伊垣直人先生(なおとさん)の3人には、たくさんお世話になりました。
ゴリさんのブログでPAを知り、KAIさんにはゲーム合宿やその他たくさんのところで実際に行う姿を見せていただき、なおとさんはPAJの研修の際にじっくりいろんなことを教えていただきました。この3人無くして、自分が教室でPAを行うイメージは生まれなかったと思います。
この3人はそれぞれ三者三様に教室の中にPAを取り入れていました。
それによってクラスが変わっていく姿もたくさん目にすることができました。
今、PAに興味がある、教室に取り入れてみたいと考えているあなたも、この3人のように実際に教えてくれるメンターのような存在を持つことをお勧めします。
PAJの研修に行くといろいろな気づきを得られます。「クラスの力を生かす」は1日が基本ですし、初めての先生でも比較的受けやすい研修だと思います。

あお
ボクの学級経営の作り方は、PAにすごく影響を受けています。研修から感じたことで作った学級目標はこちら!
教室でのPAの実践① 魔法のじゅうたん

ここからは小学校5年生での実践です。
まずは魔法のじゅうたんというアクティビティです。
ルールについて説明します。
毛布大の大きさのマット(ブルーシート)に10人程度のグループで乗っかり、シートから落ちずに反対側に裏返すことができたら、課題達成です。
ルールにファンタジーの要素を加えて説明する!
ボクは当時の子どもたちにこんなふうに説明していました!

あお
皆さんは、悪人を懲らしめて財宝を民に分け与えるヒーローです!
ニヤニヤ

子どもたち

あお
財宝のありかがわかって魔法のじゅうたんで向かっていたところ、宿題忘れを懲らしめる追っ手に追いつかれ矢で射貫かれてしまいました。
今日、宿題忘れ多かったもんね(笑)

子どもたち

あお
じゅうたんに乗ったまま、裏返して、矢に射貫かれた場所を修理しなくてはいけません。じゅうたんの耐久性から考えると20分以内に修理しないとじゅうたんは落下してしまいそうです。みんなでトライしてみよう。
こういうファンタジー的な要素は、実はアクティビティの中でかなり重要だと思うんです。より多くの子を舞台にのせる…という意味でも。
アクティビティ自体に力があるので、始まってみればそれはそれで、勝手にのっていくんだろうけど。。。
それでも一人でも多くの子が、スタート地点に立つって意味で、ファンタジーの要素は必要なんですよね。
この本が詳しいです!
PAのアクティビティスタート!
3つのチームに分かれてスタート。
簡単だと思っていた子どもたちは、やってみるとその難しさに驚いていました。
あっという間の20分。
途中、対立もあったけれど終了。
達成は1グループ。
達成できなかったところが2グループありました。

あお
間違えても達成させようとアドバイスするなどはやめましょう。
プロジェクトアドベンチャーの大事な要素 振り返り

あお
先にソロで振り返ってからでも良いし、グループからでもOK。必ずみんなで話す時間は入れてね。
振り返りスタートで、子どもたちの話に耳を傾けます。
達成しようとする気持ちに差があるよね…

子どもたち
そこから全体でも掘り下げて、振り返りを聞いていこうと思いました。
ちょこちょこ意見が出てきましたが、ある子がこんなことを言ってくれました。
それぞれゴールへの気持ちに差があった。私は達成したかった、だから男子に対して強く言ってしまった。そんな自分もどうかと思う…

あお
達成しようという思いに差があるのは当然。ぼくらはいろいろな場面でそうだよね、みんなが同じなんてありえない。
そんな時、ボクらはどうする?
新たな問いに対して、ぽつりぽつりと話してくれる子たち。
「対立するのはそのままでいい。ただ注意しすぎないことも必要。」
「自分が想っていることをしっかりと相手に伝えるなら、対立もOK。」
「お互いのことがわかる対立って大切。」
「『ふざける』と『楽しむ』は違う。みんなでその差を意識する。」
などなどが出てきました。
女子の勇気を出した一言がクラスの雰囲気を変え、対立していたチームの子も、考え振り返りを話してくれました。
少しずつですが、対立に向き合うことができている。
クラスが一歩進んでいる…そう実感した瞬間でした。
振り返りジャーナルに書かれていたこと
私は達成するためには、何回でもチャレンジ、人の意見をよく聞く勇気を出して自分の意見を言うのが必要だと思います。
なぜなら何回もチャレンジは何回も失敗したけどあきらめないでチャレンジをし続けたら成功しました。
「人の意見をよく聞く」
自分のことだけに精一杯にならず、人の意見を聞かないと、次に何をするか分からなくなるからです。
「勇気を出して自分の意見を言う」では自分の意見を出さないと、自分の考えてることがわからないので自分の意見を言うことが大事だと思うからです。
今日は魔法の絨毯がありました。とりあえずやってみたけど、出てしまいました。幅広いけれど、絨毯をし繰り返す時に、ジャンプしにくいのかなと思いました。俺の10分で話をしました。自分でどんどんやる人と、その指示に従っている人がいるのに気づきました。私はそれがやる気がある人とない人の差なのかなと思いました。必要な事は人の意見を否定しないで、まずやることが必要だと思います。
あとみんなの違いを認めると言うことも大切だと思います。ふざけたことをしていると言う人がいると聞きました。その人が自分でも避けたいと言ってました。強く言い過ぎてしまって喧嘩になってしまって思いました。
みんなの違い認めることが難しいと思いました。
僕は、確かにやる気のあるクラスの人とふざけたりしているマイナスの人がどちらもいないといけないと思いました。何故かと言うと電気を±どちらもなければ電気は取りません。なので±と言う表現の仕方わかりやすかったです。一人ひとりの違いを知りながら日々生活します。
私は今日の課題が達成できたのは、まずやってみる。あきらめない、時間がなくても落ち着いて。簡単そうでチャレンジゾーンにあるものができたからだと思います。これから落ちてしまって、「なんでおちてんの」「あーもうダメだ」と言うマイナスの言葉が多かった。ですが○○さんなどのことで笑えたのも必要だったじゃないかなと思いました。
みんなの違いを認めると言うことはとても大事だと思いました。なぜなら体が大きい人はこっち、小さい人はこっち、面白いと盛り上げてくれる、意見を出すのが得意な人を中心に考える自分から声を出さない人はみんなから声をかけてあげる。そんなことが大切だと思ったからです。
私はクラスには十人十色、いろいろな人がいるから、とても難しいと思うけれど、やはり達成しようと言う思いが強い人弱い人がいてそれを全て同じにするのがとても難しいと思うけど、もう少し意識をあげて欲しいなと思いました。
また私ももう少し心を広くし、想像力のスイッチを入れたいなと思いました。
一つ一つの振り返りを読みながら、ちょっとずつ前進しているのが伝わってきました。
教室でのPA実践② ヘリウムリング

先週は、大学教授のきみさん、インプロパークのすぅさん、そして学生たちを迎えて、クラスの授業を公開しました。
「クラスを開くこと」
ボクにとっては大きなハードルですが、様々なフィードバックがいただけると思い、今回引き受けることにしました。
ちょうど今年度の4月、出会った二人の方に、年度の最後に来ていただけるなんて嬉しいですね。
前回は、「課題達成に向かう温度差が違うときに、どうするか」ということについて、クラスの中で振り返りを出し合いました。
今回は新学習指導要領も細かく読み込んで、この段階まで来ている子どもたちに何が必要なのか、考え抜いて授業に臨みました。
ボクは道徳専門ではないので確かなことは言えないのですが…次の内容について、子どもたちがしっかりと議論する授業にしたいと思いました。
学習指導要領とどう絡めるか、しっかり決めて臨んだんだね。

まーくん

あお
重なるところはあるものの、決めて臨むことで、固くなっちゃうものは生まれるなぁと反省です。
学習指導要領から
この段階においては,これまで以上に友達を意識し,仲のよい友達との信頼関係を深めていこうとする。また,流行などにも敏感になり,ともすると趣味や傾向を同じくする閉鎖的な仲間集団を作る傾向も生まれる。そのため,疎外されたように感じたり,友達関係で悩んだりすることが今まで以上に見られるようになり,このことが不安な学校生活につながる状況もみられる。このことから,友達同士の相互の信頼の下に,協力して学び合う活動を通して互いに磨き合い,高め合うような,真の友情を育てるとともに,互いの人格を尊重し合う人間関係を築いていくようにすることが求められる。
指導に当たっては,健全な友達関係を育てていくことが一層重要になる。この段階が第二次性徴期に入るため,異性に対する関心が強まり,これまでとは異なった感情を抱くようになる。この異性間の在り方も根本的には同性間におけるものと同様,互いの人格の尊重を基盤としている。異性に対しても,信頼を基にして,正しい理解と友情を育て,互いのよさを認め,学び合い,支え合いながらよい関係を築こうとすることに配慮して指導することが大切である。
「上手くいかないときや対立が起こったときに、どんな考えが必要だろうか」をテーマとしてやりましたが、寄せてしまった分のプラスとマイナスについては振り返りました。
アクティビティ「ヘリウムリング」
こちらもKAIさんの本が詳しいです!
ルールはこちら!
1グループ10人程度でフラフープを用意します。
人差し指を横にする形で頭上近くのフラフープを支えます。
そこから誰の指からも離れること無く、地面にフラフープをつけられたらクリア。
もちろん失敗はOK。何度でもやり直し構いません。制限時間は20分です。
今回もファンタジーの要素を入れました!

あお
前回まほうのじゅうたんをクリアできたみんなだったが、僕らの仲間が捕まってしまった。救出したければ、この魔法のリングを使って、仲間をリングに通して欲しい。でも魔法のリングには使い方があって…
ヘリウムリングのアクティビティスタート!
結構簡単そう!!

子どもたち
どのグループもそんな感じからスタートしましたが‥
今回、3種類フラフープを準備しました。
重さがあるフラフープ、軽めのフラフープ、ジョイントタイプのすごく軽いフラフープ。
今回使用したのは、軽めのフラフープです。実はこのアクティビティは軽ければ軽いほど、難易度があがります。人数が増えれば増えるほど難しい…
「上手くいかないとき」や「対立が起こったとき」を仮定して考えているので、重いフラフープじゃ簡単だと思ったのです。
予想通りなかなか上手くいきません。でもやはりここまでのPAや体験学習サイクルの積み重ねがあるので、どんなことも試す姿勢で、笑顔でやるなぁというのが、この日の第一印象。
対立までは起こらないまま進んでいきます。それは成長なのか、まだ成熟していない段階なのか。
結局、制限時間20分の中で、実際にできたのは1グループでした。しかも「対立」が起こらないような良い雰囲気の中で…
このグループには、前日にいろいろあったメンバーが全員入っていたので、かなり驚きました。ぐいぐいリードしていたのは、そのメンバー。
子どもの底力に驚かされました。
他のグループは、「もやもや」が生まれているようでした。
プロジェクトアドベンチャーにおける振り返り
成功したグループは、自分たちの「良かったところ」を中心に挙げていました。
やっぱり失敗しても笑顔で、次に気持ちを向けてたところ。

子どもたち
わいわいした様子で振り返りが進んでいきます。
一方失敗したグループはお通夜状態。
誰かを責めることはないのですが、雰囲気はかなり暗かったです。
ボクも1つのグループに入って問いを投げかけてみました。それと同時にこのグループで出てきたことを全体の場でも扱いたいなぁと思いました。
この年、インプロパークのすぅさん、そしてインプロを学ぶ多くの方と出会ってから、ボクは「即興」でものごとを創り出すことを大事にしています。
成功したのは、笑って楽しんだから、笑いが成功を生んだと思います。
アクティビティがなかなか難しかった。こういう緊張が高い場でも、言い合える雰囲気を作りたい。
試すことに夢中になってそれがずっと続いてしまった。もっと途中に作戦会議を入れたい。
失敗したときでも声をかけることは大切。
子どもたちの発言の中で、「声をかける人が少ない」というところを取り上げて…

あお
前回は「課題達成のための温度差」が上がってきたけど、今回は「意見を言う人と言わない人」があがってきたよね?それについて、意見をたくさん言う人と、そうで無い人と両面から、できることはあるだろうか?
その問いについて近くの人と話した後、出し合ってもらいました。
意見を言える人側として…
気づかい、周りを見て声をかけること
笑いがある感じをつくること
「ひとりずつ言ってみよう」と話をふること
些細な表現を拾うこと
そして意見を言えない側としては、なかなか発言がありませんでした。
「自分は言わなくていいや」という気持ちがあった、と話してくれました。
最後に先生から‥

あお
意見を言う人と言わない人、両方クラスにとっては大事なんだ。だからこそ、言わない人はどうしていくことができるか、みんなで考えたいから、この後ジャーナルに書いてね。どちらか片方じゃなくて、お互いが相手のことを考えて、その場に応じて、行動に移していくのが大切だと思いました。これから続く行事で上手くいかないことがあったら、そのときには今日のことを思い出して試してみよう。
参観していただいた先生からのフィードバック

あお
どんなクラスに見えました?
「自分の中の感覚に、耳を済ませられる静けさのあるクラス」
「わだかまりに向き合いながら、ゆっくりそれそれを溶かしていくクラス」という言葉が思いつきました。 活発に意見を言い合いお互いを助けあっている様子も印象には残っているのですが、青ちゃんのクラスにしかない、「これ!」というものを挙げるとしたら、私はそれかな。
Facebookの記事にも書きましたが、「道徳」の時間のときに、子どもたちがつらそうな顔をして、静かな声で語っている様子が印象に残っています。また、その中で、笑いあえるような雰囲気を作ることが大切だ、という意見が子どもたちから出てきたことについても、すごく考えさせられました。 みんなが、自分の中の、生の経験と向き合っている…生の経験を真摯に言葉にすればそれは受け入れられると信じているし、それが実際に受け入れられている。 そのこと自体が、本当に、すごいことだと思いました。 だからこそ、聞こえ方によっては、意見を言えない子どもを傷つけてしまいかねない発言も、単なる攻撃の言葉にならずに、その場所に根を下ろしていくのですよね。 言葉を発するその子自身も、その言葉を発することでなんらかの痛みを負っていることが、聞き手にも伝わっているから。
自分と他人が異なることが前提ではあるけれども、わかりあえない(かもしれない)人間同士として、相手を理解しようとすることを、あきらめない。 「チームビルディング」とか「他者理解」とかそういお題目が虚しく響くくらい、ラディカルなかたち《ともに在ること》を探求する関係性が作り出されていて、このコミュニティの成り立ちや今後をもっと知りたいな、と思いました。
この時のクラスは、まさしくつながりを意図的にデザインし始めたクラス、その強さっていうのが出ていたのだと思います。
先生の号令でピシッと動き回るクラスなんかでは無く、一人ひとりが振り返りを軸として、自分の体験学習サイクルを回しているクラス。それでいて周りの子の力を借りたり貸したりして、ナチュラルにお互いにも関われる。普段は自分のことを大事にしているけど、行事とかになると、お互いのことを大事にして、大切に考えて、集まったときも力を発揮できる…そういう自然なクラスでいたいなぁと常々思っています。
「道徳」では、ある子どもたちにとってヘリウムリングが、別の教材性をもっていたな…と感じる場面がありました。 大学生がそのこといついて、私とはまったく逆の立場から指摘していて驚いたのですが、わたしはヘリウムリングでの子どもたちの活動や振り返りを見ていて、これは、「うまくいかないとき、対立が起きたときどうするか?」というよりも、「あるゴールが示されてみんなでそれに向かっているとき、そこからドロップアウトしてしまう人たちやその思いをどう集団ですくいあげていったらいいのか?」という点にフォーカスした活動だったのではないか?と感じました。 うまくいかなかったチームの方が多かっただけに、「対立したときどうするか」「うまくいかないときどうするか」という当初に示された目的が、お互いを傷つけあうような振り返りへとつながってしまった。示された目的が、それであったことで、「言えなかった子」が、自分の感じたことを「ねらいとは関係ないから言うべきではない」と感じた、言い出しにくかったということはあったのかな、と思いました。
まさにズバリと言い当ててもらいました。
道徳の場合、必ず最初に課題があります。こちらとの整合性をはかりにいった分、やはりそこが不自然な形になってしまって…ボク自身はすぅさんの影響もあり、即興で「意見を言う人、言えない人の違いについて考える」ことに焦点をあてて振り返りを進めました。
最初の課題とそことがぶつかり、中には言いにくそうにしている子もいました。
教室でのPAの実践③ エブリボディアップ
さっそく授業参観プロジェクトを募ったところ、あっという間に6人が立候補。一緒に授業づくりを開始しました。
プロジェクトについては、こちらの記事をどうぞ!
一緒に授業参観を創るのは、ボクも初めてのチャレンジ。
まずはクラスの状態をみんなで確認。
「ボクらが課題としたいのは?」
やっぱり「声なき声を拾いたい」っていうのが一番らしい。
意見を言ってくれる人と、抑えちゃう人がいて、でも両方大事。じゃあ、お互いに何ができるか、もう一回課題達成型のアクティビティで挑戦しようということになりました。
ここで初めて全員参加でのアクティビティに挑もう!ということになり、いくつかの中から子どもたちが選択したのは、「エブリボディアップ」。
ルールを確認し、振り返り担当も決め、準備万端!

あお
こんな頼もしい言葉も!
プロジェクトアドベンチャーで授業参観

たくさんの方が来てくださる中での授業参観でした。
めあては次の通り。
意見を言える雰囲気を作りながら、全員達成を目指そう!
ルールは次の通りです。
- お尻が床にしっかりとついている。
- 手や腕が他の人とつながっている。(全員が何らかの形でつながっている)
- 足が両足とも他の人に触れている。
- 一斉に立ち上がる。
子どもたちのチャレンジがスタート。実行委員を中心に作戦を立てて、何度も挑戦していきます。これがなかなか難しくて上手くいかないことが多い。しかしながら、少しずつ意見がまとまって、惜しい瞬間がたくさん出てきて…
子どもたちは声をかけるし、雰囲気は悪くない。でもできない。。。。
結局タイムアップ!
振り返りで出てきた言葉
振り返りも子どもたちで、テーマはその場で一緒に相談して決めました。
全員で何かをするとき、いろいろな人の声を拾うために、大切にしたいことは?
子どもたちの意見は、次のように出てきました。
- 人に任せて意見を言うのではなくて言う
- 周りの人だけではなく、多くの人に伝える
- 近くの人と工夫できた
- 手を挙げる以外の方法を大切にする
- 積極的に言う
- サークルになるように声をかける
- 物を回す、指名以外の言い方
- 明るい雰囲気を大切に
- 意見と試すことのバランス
- 殻を破ることも大切
- まとめてくれる人がいて良かった
子どもたちの具体的な言葉で語られた意見が、次の行動をきっと作っていくと思っています。

あお
ここからは今考えて思うこと。
PAって、道徳の授業のように最初からテーマを焦点化するものじゃないと思うんです。ヒミツキチ森学園でもたくさんPAをやっていて、この間もイベントで子ども18名ほどを相手にPAをやり、振り返りました。
ボクはファシリテーターとしてその場で感じたことを大事に問いを投げるし、子どもたちがまずは自分の話したいことを話す場であってほしいなぁと思っています。
この辺りのさじ加減は、この実践から6、7年が経って思うことですが、やはり最初からテーマを絞っているのは、ちょっとPAの趣旨とは違うよなぁって思います。
授業参観を一緒にやってみて感じたこと

実際にやってみてのことを記録しておきます。
クラスでボクが取り組んできたこと、まさしくそれが伝わっていたことが嬉しかった。来年は学年に広げて実施予定。
授業参観では結果としては、上手くいかなかったけど、その様子は授業を通じて保護者に伝わっていたみたいで嬉しかったです。
「人間関係の流動性」を大切にしていることを保護者にも丁寧に伝えました。
また「子どもたちが授業を創って自分たちでやれる堂々とした感じが頼もしかった」…との声も。
実はこの翌日、クラスは長縄大会で新記録を出しました。無茶苦茶忙しくて、練習する暇が無かったのですが、一つのことに向かっていくのは、エブリボディアップと一緒。
成果というのは目に見える形じゃ無くて、個人を中心にいろいろと溜まっていって、ふとしたときに溢れ出てくるもの。
誰かにとっての成果は、また別の誰かにとっての成果と一緒とは限らないということ。
クラスで振り返ったときに出てきた子どもたちの言葉です。
成長は一直線じゃないと思うんです。
それぞれがちょっとずつ自分の成長をすることで一つのところに向かっていったり、
むしろ矢印は一つに向かっていかず、あらゆる個の伸びがそれぞれの色をもっていて、結果として一つのことの成果が生まれる…そんなイメージでしょうか。
だからこその「ビーイング」であり、個の信頼の積み重ねでクラスを創っていくことが大切になってきます。
リベンジしたい!エブリボディアップに再挑戦!

さて、その2日後、授業は道徳の時間。
再チャレンジです。
ボクはこの日、次のことにだけ触れようかどうかずっと考えていました。
それは…
思い込みを外すこと。
結局最初には触れず、子どもたちに任せてみました。
この日のチャレンジ時間は25分。ただ10分を過ぎたあたりで、やはりそこに触れてみようかなぁと思い直し、中断しました。

あお
ねぇ、なんかみんなの中に「思い込み」があるような気がするんだけど…その「思い込み」を外すことがみんなには必要なことかもしれないって思うんだ。
誰かが気づいた…
でもすぐには形にはなってこない…
焦らずその場に任せることにしました。
いくつかの意見の後、ひとりの子が言いました。
ねえ、いったん、この円やめて、2列でやってみない?

子どもたち
ちょっと場の空気が変わったのを感じました。
半信半疑で、やってみるものの、やはり上手くいかない。
2列で向かい合ってやっているのですが、なかなか上手くいきません。
そこである子の一言。
ねぇ、横の人と手をつなぐんじゃ無くて、前の人とつないでみたらどう??

子どもたち
「おぉーーーーー!それいいね、やってみよう」
「ルール的には問題ないよね、先生?」

あお
ルールに書かれてないから、問題ないよ。
惜しい、数回、惜しいのが続いて
ついに一斉に立ち上がることが出来ました!!
やったぁーーー!

子どもたち
長縄大会以上の喜び具合でした。
大切なのはアクティビティの後の振り返り

授業参観プロジェクトのメンバーと、振り返りの内容について決めていきます。
今回のテーマは
(今回は)何があって(理由で)達成できた?
日本語は変だけど、子どもたちに意味は伝わっているはずです。
振り返りは、子どもたちが一人ひとり話したのを、ボクが板書しました。
- 一人ひとりが意見を言うのを続けていこう
- 振り返りの積み重ねが大切、前回があったから今日の成功がある。
- 話し合うことに価値がある
- 今回のアイディアは、4人でやったときのを元にしているから、行き詰まったら、最初に戻ることも大切。
- ルールを見直すことが大切。
- 今回も自分たちで決めれた、みんなで話し合って決めることが大切。
- 前回から考える時間があって、それで考えてきたアイディアが良かった。
- 雰囲気の明るさはみんなでつくるってこと。
- 成功させたいっていう気持ちが必要。
- 意見を混ぜ合わせること。今日は二人の意見が混ざった。
- 楽しさは必要、だけど真剣な楽しさが大事。
- 思い込みを無くしたい。
- 今日は意見が言えた!そういう雰囲気があった。話を聞いている人の感じも良くて話しやすかった。
全員で課題達成の後、ボクも「思い込み」について話しました。内容は、「自分への思い込みを外すと起こること」だったと思います。
また一歩進んだかなぁ。
私は今日達成できた理由は、アイディアを出してくれたのに、どんどん積み重ねて、最高のアイディアが作れたからだと思います。たとえば○○さんの円じゃない考えに、○○さんの手のつなぎ方のアイディアを付け足して、成功できたところです。
私は次に真剣な楽しい雰囲気が作れると、普段意見が言えない人も言いやすくて良いと思います。クラスの仲間で、いつも敬語を使っていないので、ラフな感じを作りたいです。
ぼくはみんなが一つのことに向かってやれば、いろいろな意見が入ってくるし、まとめる○○さんは、「とても大変だったのかなぁ…」と思います。そしてみんなが意見を言ってくれるのはいいんだけど、その意見に対して「できなくない?」と言っている人がちらほらいるの。そこを気をつけたいのと、一回一回個人で試している人がいたので時間がもったいないと思いました。また合間に話している人がいたので、回数が減ってしまったのかと思います。
次への課題も見つけ出していました。
一回で「できた」「できない」じゃなくて、できないことも大切。そこに向き合って振り返りを続けて来たことで、そこに向かっていく力もついてきているのだと思います。
クラスでの振り返りも、個人での振り返りも、愚直に積み重ねていくことが大切ですね。
5年生での教室での一幕です。
振り返りを重ねて、この年の子どもたちは対話できる関係性を築いていきました。それが次の学年での自信にもつながっていたと思います。
プロジェクトアドベンチャーの学校における価値

実践を踏まえて感じていることをいくつか紹介していこうと思います。
心理的安全性が高まる
まず笑いあえる教室は心理的安全性が高いということ。
さらに言うと、子ども同士の間にある、心の壁をどう取り除くかという課題を上手く解決してくれるのがPAだと思っているのです。
これはいくつかの本にも書かれていることなのですが、楽しいレクをすることで、ふっとその壁が下がる瞬間があるんです。うっかり手を繋いでみたり、人の手助けをしてみたり。そんなうっかりがPAというレクを通じて起こる可能性が高い。
そうすると、誰かの心の壁をちょっと下げることになる。自分の壁って自分じゃ下げられない。でも協力したり、笑いあったり、ついうっかりが起こる状況だと、自分の行動で他の人の壁を下げることになります。それが相互に作用しあって、結果的にみんなの壁が下がっていく。

あお
教室でPAをやったことのある人にはそう言う感覚や手応えがあるのではないでしょうか。
だからこそ教室びらきの時期には、たくさんのPAを取り入れます。
ネームタグとかもその一例。
壁をお互いに下げ合うことで、心理的安全性が確保されます。
こちらは鉄板アイスブレイキングとして記事にしました!
場づくり、雰囲気づくりがこれからの先生には求められる
いろんな本の中でも語られていることですが、AIにより働き方は大きく変わっていきそうです。
AIに任せながらも、先生という職業は形態は代わるにしろ、無くなることはないでしょう。もしかしたら授業における先生の役割は少しずつ少なくなっていくのかも知れません。
しかし教室の関係性を作ったり、人と人とのつながりをつくったりする役割は、これからも間違いなく残り続けるでしょう。こういうケアの部分の役割が増えてくるような気がしているのです。
ヒミツキチを始めて間違いないね!

まーくん
「教える」から「環境を創る」「つながりを創る」へ、そうなった時に場をどう創るかが、ボクらの大きな課題になる気がするんですね。
そこでPAのような場を創る、雰囲気を創る手段は、きっと先生という職業だけじゃなく多くの現場で必要になってくるのではないでしょうか。
PAには「アイスブレイク」から「イニシアティブ」まで、様々な種類のアクティビティが用意されています。それをどう組み立てるかも、ファシリテーターの腕の見せ所です。
ケアについては、こちらが詳しい!
コミュニケーションが多様になる
そんな場作りの先にあるのは、活発なコミュニケーションです。
イニシアティブのアクティビティ1つをやるにも、課題達成のためにたくさんの対話が必要になります。課題達成という目標があるため、必然的に対話を重ねないといけません。
もちろん、学習の中にこの環境があればいい、つくれればいい。でもそう簡単に必然性を作れないのは、先生方ならわかっていることでしょう。
PAのアクティビティを効果的に用いることで、学習の中にもそれが起きやすくなるのは確かです。アクティビティの後の振り返りによって、日常のコミュニケーションにもちゃんとつながっていくのです。
PAの場ではできるのに、普段はそれが足りないよね…それは、もしかしたら振り返りが機能していないかもしれません。体験学習サイクルを回し、日常への浸透もはかっていくことができます。
プロジェクトアドベンチャーの関連本

ここでは関連書籍をあげておきます。
書籍やPAJの研修でぜひぜひ学んでみてください!
まとめ プロジェクトアドベンチャーの可能性

PAについて、ボクの考えや実践を書いてきました。いかがだったでしょうか。
PAの理念の中に、大切な二つがあります。
それは、Full Value Contract(FVC)【フル バリュー コントラクト】と、Challenge By Choice(CBC)【チャレンジ バイ チョイス】です。
PAJのホームページから引用です。
【フルバリューコントラクト】
PAプログラムでは、プログラムを始める前に簡単な約束をしてもらいます。
これをフルバリューコントラクトといいます。これは、お互いの努力を最大限に評価するという約束です。
つまり、「自分を含めたメンバーをけなしたり、軽んじたりしない」、具体的には「お互いの心の安全と身体の安全を守る」、「自分に正直である」、「ネガティブなことにこだわらない」などがあげられます。
【チャレンジバイチョイス】
PAプログラムには強制はありません。
挑戦への選択の自由が常に保証されています。個人の挑戦レベルとその方法は、自分自身が決定します。
また、自分が挑戦を選択しなかった場合でも、グループから外されるのではなく、グループの仲間にどのような方法で協力できるのかを考えることも選択のひとつになります。
両方とも非常に重要な考えです。
さて、あなたがこれからPAをやってみるのも「チャレンジ・バイ・チョイス」です。
まずはアイスブレイクのアクティビティから試すってことも大事。どんな一歩をきるか自分で選んでいきましょう。

あお
それでは今日も良い一日を!
プロジェクトアドベンチャーも取り入れる楽しい学校を仲間と作っています!




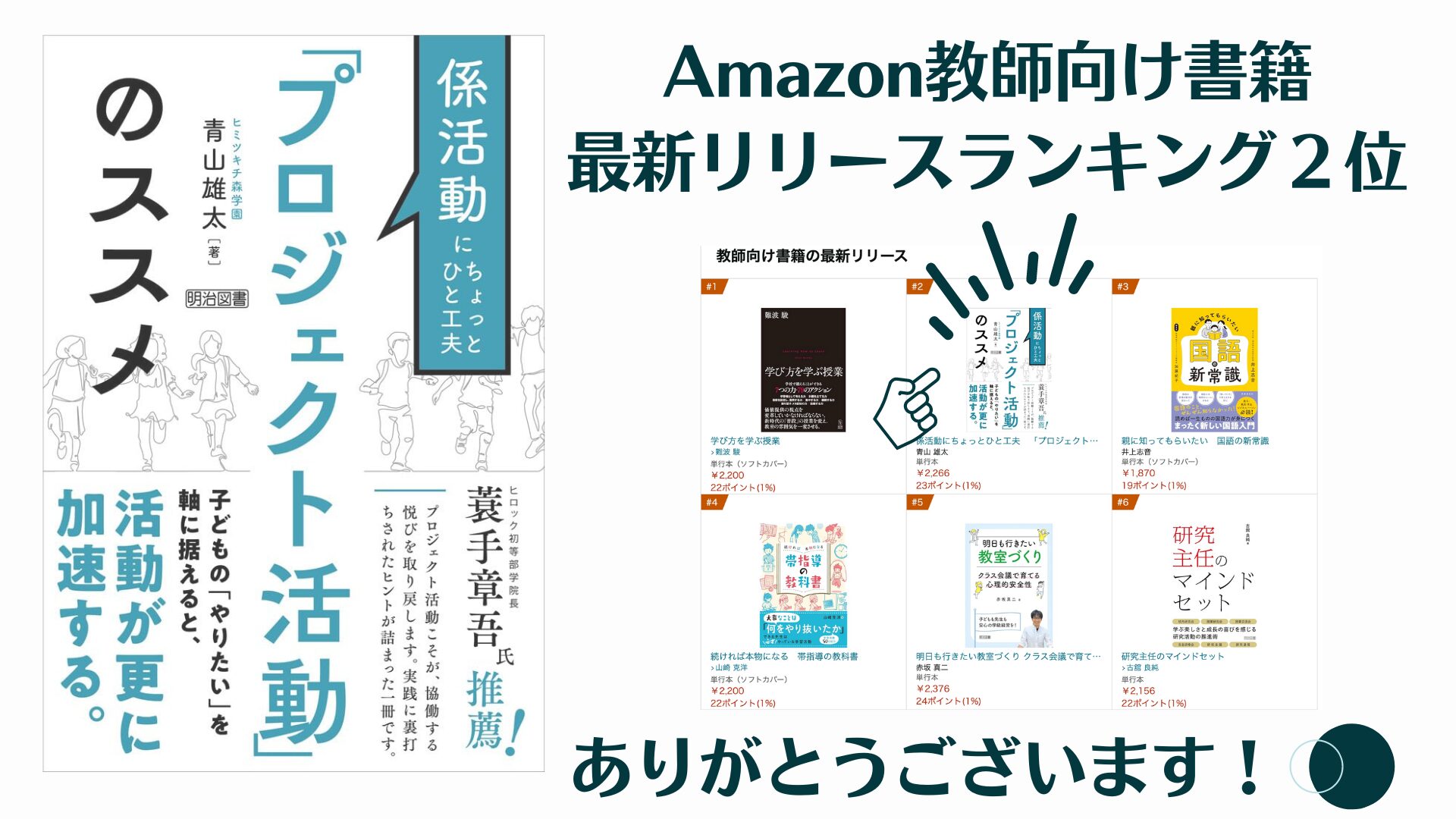















1 件のコメント